エレキギターに必ずと言っていいほど付いている「トーン」のノブ。
しかし、「いつもフルテン(10)のままで触らない」「正直、効果がよく分からない」と感じ、「ギターのトーンはいらないのでは?」と疑問に思っている方も少なくないでしょう。
実際、プロのギタリストの中にもトーン回路を外してしまう人がいる一方で、巧みにトーンを操り多彩なサウンドを生み出すギタリストも存在します。
この記事では、長年議論されてきた「ギターのトーン不要論」の真相に迫ります。
トーンの役割や仕組みといった基礎知識から、トーンをなくす「トーンカット」改造のメリット・デメリット、具体的な配線方法、さらには積極的なトーンの活用術まで、専門的な視点から網羅的に解説していきます。
「ギターのトーンはいらない」は本当?プロの意見と賛否両論を徹底解説
「ギターのトーンはいるか、いらないか」という議論は、ギタリストの間で長年交わされてきました。
結論から言うと、これは一概にどちらが正しいとは言えず、個人の好みや演奏スタイルによって答えが分かれます。
ここでは、それぞれの主張とプロの事例を見ていきましょう。
そもそも「トーンはいらない」派の主張とは?
トーンが不要だと考えるギタリストの主な主張は、「音が劣化するから」というものです。
ピックアップからの信号がトーン回路を経由するだけで、たとえノブがフルの状態であっても高音域がわずかに削られてしまい、本来のサウンドが損なわれると考えられています。
また、音作りはアンプやエフェクターで完結させるため、ギター本体での調整は不要という意見も多く見られます。
「トーンは必要」派の主張とは?
一方、トーンは必要だと考えるギタリストは、そのサウンドバリエーションの豊かさを重視します。
トーンノブを少し絞るだけで、耳に痛い高音域を抑えたり、甘く太いリードサウンドを作ったりと、手元で瞬時に音質を微調整できる点は大きな利点です。
ライブ中にアンプまで移動できない状況での微調整や、1曲の中で複数の音色を使い分けたい場合に重宝します。
有名ギタリストに見るトーンノブの活用事例(ジェフ・ベック、E・ヴァン・ヘイレン等)
トーンノブを巧みに操るギタリストとして、故ジェフ・ベック氏は非常に有名です。
彼はボリュームとトーンを駆使して、ピッキングだけでは表現できない繊細なニュアンスを生み出しました。
一方で、エディ・ヴァン・ヘイレン氏は初期の自作ギター「フランケンシュタイン」でトーンノブを排除し、ボリュームノブのみというシンプルな仕様を採用していました。
しかし、後のシグネイチャーモデルではトーンノブが搭載されており、彼自身も「あれは間違っていた」と語っていたことは、トーンの有用性を示す興味深いエピソードです。
【結論】あなたのプレイスタイルや音楽ジャンルによって必要性は変わる
結局のところ、ギターのトーンが必要かどうかは、あなたがどのようなサウンドを目指し、どのような音楽を演奏するかによります。
常に高音域が突き抜けるシャープなサウンドを求めるなら不要かもしれませんし、多彩な表現をギター本体でコントロールしたいのであれば、非常に強力な武器となるでしょう。
なぜ「トーンはいらない」と言われる?音が劣化する?3つの理由

「ギターのトーンはいらない」という意見には、いくつかの具体的な理由が存在します。
なぜ多くのギタリストがトーン回路の存在を疑問視するのか、その背景にある3つの主要な理由を解説します。
理由1:回路を通るだけで高音域が失われる(ハイ落ちする)から
最も大きな理由は、トーン回路が接続されているだけで、音質、特に高音域が劣化する「ハイ落ち」と呼ばれる現象が発生するためです。
トーンノブを「10」にしていても、ピックアップからの信号の一部はトーン回路(ポットとコンデンサー)に流れ込み、高音成分がわずかにアースに落ちてしまいます。
これにより、本来ピックアップが持つ最も煌びやかな高音域が失われ、音がこもったように感じられることがあるのです。
理由2:アンプやエフェクターで音作りが完結するから
現代では、高性能なアンプや多彩なエフェクターが数多く存在し、ギタリストの音作りの幅は飛躍的に向上しました。
イコライザー(EQ)ペダルを使えば、ギター本体のトーンよりも遥かに細かく周波数帯を調整できます。
そのため、音質の調整は足元やアンプに任せ、ギター側は最もピュアな信号を送ることに徹したい、という考え方が広まっています。
理由3:ハードロックやメタルでは高音の抜けを最優先するため
特にハードロックやメタルといったジャンルでは、歪んだサウンドの中でも輪郭が埋もれないよう、突き抜けるような高音域(プレゼンス)が重視される傾向にあります。
このようなジャンルを演奏するギタリストにとって、少しでも高音域をロスする可能性があるトーン回路は、サウンドの鋭さを削ぐ不要なパーツと見なされることが多いのです。
ギターのトーンをなくす(トーンカットする)具体的なメリット

ギターのトーン回路を物理的に取り外したり、バイパスしたりする「トーンカット」改造。
この改造を施すことで、サウンドには明確な変化が生まれます。
ここでは、トーンカットによって得られる具体的なメリットを3つご紹介します。
音がよりダイレクトでストレートなサウンドになる
トーンカットの最大のメリットは、ピックアップからの信号が余計な回路を通らず、直接ボリュームポットやジャックに出力されることで、非常にダイレクトでストレートなサウンドが得られる点です。
回路がシンプルになることで、信号の劣化が最小限に抑えられ、ギター本体やピックアップが持つ本来のキャラクターが色濃く反映されるようになります。
トーンを「10」にした時以上に高音が抜けるようになる
前述の通り、トーン回路はフルテンの状態でもわずかに高音域を減衰させます。
トーンカットを行うと、この減衰が完全になくなるため、トーンを「10」にした状態よりもさらに高音域が強調され、煌びやかで抜けの良いサウンドが得られます。
これにより、音の立ち上がりが速く感じられ、カッティングなどのプレイでシャープな切れ味が増します。
音の輪郭がハッキリしピッキングニュアンスを出しやすくなる
高音域のロスがなくなることで、音全体の輪郭がクリアになります。
これにより、ピッキングの強弱や角度といった細かなニュアンスが音に反映されやすくなるというメリットもあります。
繊細なタッチを重視するギタリストにとっては、表現の幅を広げる一因となるでしょう。
要注意!ギタートーンカットのデメリットと後悔する可能性
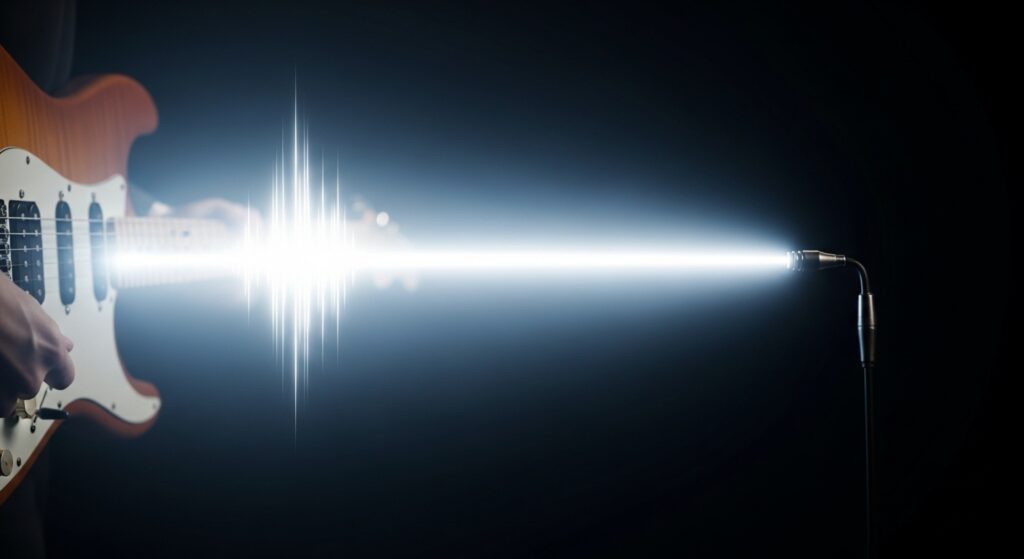
トーンカットには多くのメリットがある一方で、もちろんデメリットも存在します。
改造してから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、トーンをなくすことで失われる機能や、起こりうる問題点を事前に理解しておきましょう。
手元での多彩なサウンドバリエーションが失われる
最も大きなデメリットは、ギター本体で音色を変化させる手段を一つ失うことです。
トーンノブを絞って作る甘くメロウなサウンドや、わずかに絞って角の取れたマイルドなサウンドなど、手元で瞬時に行えた音質の調整ができなくなります。
これにより、演奏表現の幅が狭まってしまう可能性があります。
甘く太い「ウーマントーン」が出せなくなる
エリック・クラプトン氏の演奏で有名な、ハムバッカーピックアップのトーンを「0」まで絞って作る、甘く太い独特のサウンドは「ウーマントーン」と呼ばれます。
この象徴的なサウンドは、トーンノブがなければ再現することができません。
ブルースやクラシックロックを演奏するギタリストにとっては、大きな損失となるでしょう。
ライブ中のとっさの音質微調整ができない
ライブハウスの音響特性や、その日のバンド全体の音量バランスによって、「少しだけギターのハイを抑えたい」と感じる場面は少なくありません。
トーンノブがあれば手元で瞬時に対応できますが、トーンカットしている場合はアンプやエフェクターまで移動して調整する必要があります。
この利便性の低下は、ライブを頻繁に行うプレイヤーにとっては見過ごせないデメリットです。
音が「キンキン」しすぎて耳に痛く感じる場合がある
トーンカットによって得られる抜けの良い高音は、裏を返せば「キンキン」とした耳障りなサウンドになる可能性も秘めています。
特にシングルコイルピックアップを搭載したギターの場合、高音が強調されすぎてしまい、バンドアンサンブルの中で浮いてしまったり、音が細く感じられたりすることがあります。
【実践編】ギターのトーンをなくす改造・配線のやり方
「自分のギターもトーンカットしてみたい」と考えた方のために、具体的な改造・配線の方法をいくつかご紹介します。
比較的簡単なものから本格的なものまでありますので、ご自身のスキルや目的に合わせて検討してみてください。
なお、ハンダごてを使用する作業は火傷や機材の破損に繋がる可能性があるため、自己責任で行うか、専門のリペアショップに依頼することをおすすめします。
一番簡単な方法は?コンデンサーの配線をカットする
最も手軽な方法は、トーンポットに繋がっているコンデンサーの足をニッパーなどで切断することです。
これにより、高音域をアースに逃がす経路が断たれるため、実質的にトーン回路が機能しなくなります。
元に戻したくなった場合も、再度ハンダ付けすれば修復が可能です。
完全に撤去するには?トーンポットと配線をすべて取り外す
より完全にトーン回路の影響を排除したい場合は、トーンポット自体と関連する配線をすべて取り外します。
ピックアップからの信号がボリュームポットに直接向かうように配線し直すことで、最もシンプルな回路が完成します。
見た目も1ボリュームのみとなり、スッキリします。
利便性重視ならスイッチで「トーンあり/なし」を切り替える方法も
トーンを使いたい時もある、という方には、スイッチを使ってトーン回路をバイパス(ON/OFF)できるようにする改造がおすすめです。
プッシュ/プル機能付きのポットに交換したり、ミニスイッチを増設したりすることで、通常のトーン機能とトーンカットの状態を瞬時に切り替えることが可能になります。
ポット交換だけでOK!フルアップトーンポットとは?
ハンダ付けはしたくないけれど、トーンカットの効果を試したい、という場合には「フルアップトーンポット」や「ノーロードポット」と呼ばれるパーツに交換する方法があります。
これらのポットは、ノブを「10」の位置まで回すと内部の回路が物理的に切り離され、トーン回路が完全にバイパスされる仕組みになっています。
普段は通常のトーンとして使え、フルにすればトーンカットの状態になる便利なパーツです。
そもそもギターのトーン回路はどんな仕組み?
ギターのトーンノブがどのように音を変化させているのか、その基本的な仕組みを理解しておきましょう。
この知識は、なぜトーンカットで音が変わるのかを深く理解する助けになります。
トーンの正体は高音域をカットする「ハイカットフィルター」
エレキギターの一般的なトーン回路は、音響信号における高周波成分(高音域)を減衰させる「ハイカットフィルター(またはローパスフィルター)」として機能しています。
ノブを絞る(値を小さくする)ほど、より多くの高音域がカットされ、結果として音がこもった、あるいは丸く甘いサウンドに変化します。
ポット(可変抵抗器)とコンデンサーの役割とは?
トーン回路は主に「ポット(ポテンショメーター)」と「コンデンサー(キャパシタ)」という2つの電子部品で構成されています。
| パーツ名 | 役割 |
|---|---|
| ポット | ノブと連動した可変抵抗器。ノブを回すことで抵抗値が変化し、コンデンサーへ流れる信号の量を調整する。 |
| コンデンサー | 高い周波数の信号を通しやすい性質を持つ。ポットで調整された量の高音域信号をアース(GND)へ逃がす役割を担う。 |
簡単に言うと、トーンノブを回して「どれくらいの量の高音を捨てるか」をポットで決め、その量の高音をコンデンサーが実際に捨てている、という仕組みです。
なぜトーンが「10」の状態でも音がわずかに変わるのか?
トーンノブが「10」(フル)の状態では、ポットの抵抗値が最大になり、コンデンサーへ流れる信号は最小限になります。
しかし、完全にはゼロにはならず、ごく微量の信号が高音域を中心にコンデンサーを通ってアースに流れてしまいます。
これが、トーン回路が接続されているだけで音がわずかに変化する(ハイ落ちする)理由です。
「トーン不要論」から一転!ギタートーンの積極的な使い方
もしあなたが「トーンは使わない」と考えているなら、一度その積極的な使い方を試してみてはいかがでしょうか。
不要だと思っていたノブが、あなたのサウンドメイクに新たな可能性をもたらすかもしれません。
ここでは、トーンノブの創造的な活用方法をいくつかご紹介します。
歪みと組み合わせてゲインや音の太さをコントロールする
アンプやエフェクターで深く歪ませたサウンドの際に、ギターのトーンを少し絞ってみてください。
高音域のギラギラした成分が抑えられ、中音域が強調された太く粘りのあるサウンドに変化します。
また、ボリュームノブと組み合わせることで、歪みの量を手元でコントロールし、バッキングからソロまで多彩な表現が可能になります。
ジャズやブルースで甘くメロウな音を作る
クリーントーンでトーンを絞ると、角の取れた暖かく丸いサウンドが得られます。
これはジャズの演奏で多用されるテクニックです。
また、ブルースでソロを弾く際にトーンを絞れば、泣きのギターに欠かせない甘くメロウな雰囲気を演出することができます。
手元でワウペダルのような効果を出す「手動ワウ」
演奏しながらトーンノブを素早く開け閉めすることで、ワウペダルを使った時のような「ワウワウ」という効果を擬似的に作り出すことができます。
この奏法は「手動ワウ」とも呼ばれ、名手ロイ・ブキャナン氏などが得意としていました。
独特の表現力を加えることができる面白いテクニックです。
フィードバックを意図的にコントロールする
アンプの音量を上げてギターを近づけると「キーン」というフィードバック(ハウリング)が発生します。
このフィードバックは、トーンノブを操作することである程度コントロールが可能です。
トーンを絞ることで不快な高音域のフィードバックを抑えたり、逆に狙った音程で心地よいサステインを得たりと、演奏の飛び道具として活用できます。
「ギターのトーンはいらない」に関するよくある質問
最後に、「ギターのトーンはいらない」というテーマに関して、多くの人が抱くであろう疑問点にQ&A形式でお答えします。
ストラトキャスターのトーンはいらないって本当?
ストラトキャスターの「シャキッ」とした高音を最大限に活かしたいという理由から、トーンを不要と考えるプレイヤーは一定数います。
特に、ヴィンテージ仕様のストラトではリアピックアップにトーンが効かない配線になっていることが多く、その影響もあるでしょう。
しかし、ハーフトーンでトーンを絞った際の甘い音色など、ストラトならではの魅力的なサウンドも多いため、これも一概には言えません。
ボリュームノブも外してしまっても問題ない?
理論上は可能です。ピックアップから直接ジャックに配線すれば、音は出ます。
しかし、ボリュームノブは音量の調整だけでなく、歪みの量をコントロールしたり、演奏しない時のノイズをカットしたりと、非常に重要な役割を担っています。
ボリュームまでなくしてしまうと、実用面で不便を感じる場面がほとんどでしょう。
トーンを外すとノイズは増える?それとも減る?
一般的に、回路がシンプルになることで、ノイズを拾う経路が減るため、ノイズは減少する傾向にあります。
また、トーン回路は高音域をカットする性質があるため、トーンカットによってこれまでマスクされていた高周波ノイズが聞こえやすくなる可能性もゼロではありませんが、基本的にはノイズ対策として有効な改造とされています。
改造にかかる費用や難易度はどのくらい?
自分で作業する場合、ニッパーやハンダごて、配線材などがあれば、数千円以内で済むことがほとんどです。
難易度は、コンデンサーカットなら初心者でも可能ですが、ポットの交換やスイッチの増設は、ある程度の知識と技術が必要になります。
リペアショップに依頼する場合の工賃は、作業内容によりますが、5,000円~15,000円程度が目安となるでしょう。
まとめ:ギターのトーンはいらない、という考え方を整理
- ギターのトーンの必要性は、ギタリストの音楽性やプレイスタイルによって異なる
- 「不要派」は、トーン回路による音質劣化(ハイ落ち)を主な理由とする
- 「必要派」は、手元での多彩なサウンドメイクやライブでの微調整機能を重視する
- トーンカット改造には、音がダイレクトになり高音の抜けが良くなるメリットがある
- 一方で、ウーマントーンなど特定の表現ができなくなるデメリットも存在する
- 改造方法は、簡単なコンデンサーカットからスイッチ増設、ポット交換まで様々である
- トーン回路は、高音域をカットする「ハイカットフィルター」として機能している
- トーンを「10」にしても回路を経由するため、厳密には音がわずかに変化する
- ジェフ・ベックのように、トーンノブを駆使して独創的な表現を生み出すギタリストも多い
- 最終的な判断は、自身の目指すサウンドを基準に、メリットとデメリットを比較して決めるべきである

